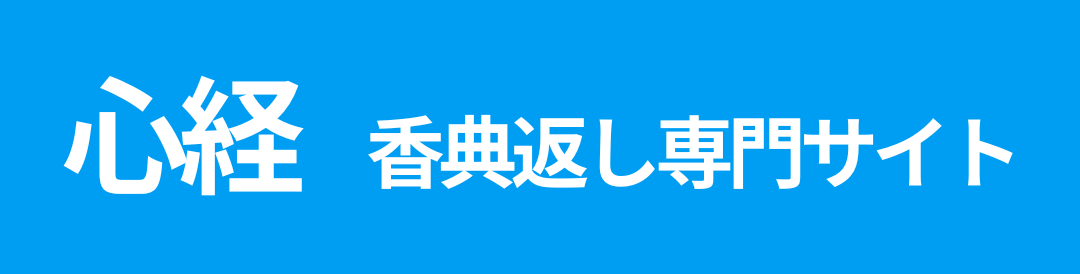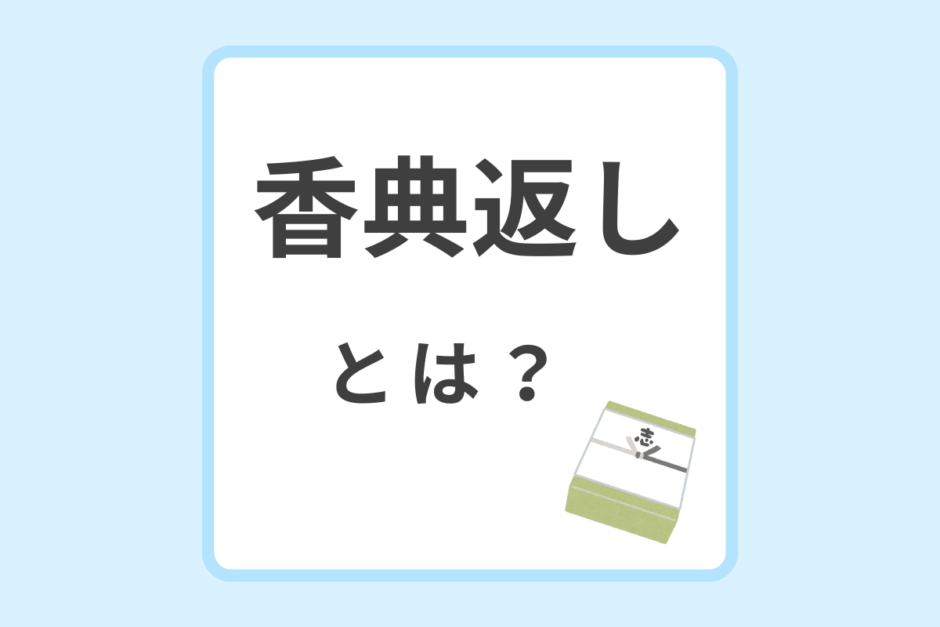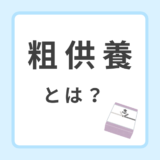香典返しとは
香典返しとは、葬儀や法要で香典(お悔やみとしていただく金品)を受け取った人に対して、その感謝の気持ちを込めて贈る返礼品のことです。
頂いた善意に対し、感謝と故人の供養の意味を込めて「つまらないものですが…」という日本らしい謙譲文化から生まれた習慣です。
香典返しの目的とは
- 香典をいただいたことへのお礼
- 故人の供養としての意味合い
- 社会的礼儀としての形式的な返礼
香典返しのタイミングとは
- 即日返し(葬儀当日)
通夜や葬儀の受付時に香典をいただいたその場でお返しを渡す形式。
軽くて持ち帰りやすいものが選ばれやすい。 - 後返し(忌明け後)
四十九日や一周忌などの法要が終わったあとに、郵送などで贈る方法。
より丁寧とされ、関東では主流。
香典返しの相場とは
一般的には、いただいた香典額の半額程度(いわゆる「半返し」)が目安です。ただし、地域や宗教、家の考え方によっては、3分の1程度に抑えることもあります。
高額の香典に対しては、上限を設けて同額のお返しを避けることもあります。
香典返しの品物とは
・お茶(緑茶・紅茶)
・和菓子・洋菓子の詰め合わせ
・タオルやハンカチのセット
・洗剤・石鹸などの日用品
・カタログギフト(近年最も人気)
「使ってなくなるもの(消え物)」が好まれます。理由は、不幸を「後に残さない」という考え方からです。
香典返しと粗供養の違いとは
香典返し:香典をいただいたことに対する返礼
粗供養 :法要や葬儀に参列してくれたことへの感謝の品
同時に用意されることもあり、香典返しに「粗供養」と印字されていることもありますが、本来の意味や対象が異なります。
香典返しの地域差とは
・関西地方では「即日返し」が主流で、葬儀当日に品物を渡す形式が一般的
・関東地方では「後返し」が多く、忌明け後に郵送で贈るケースが多い
宗派によっても異なり、浄土真宗など一部宗派では「香典返し」という言い方を避け、「返礼品」と呼ぶこともあります。
ご希望があれば、以下も説明できます。
- 香典返しの挨拶状・礼状の書き方
- 宗派や地域別のマナー
- 金額・品物の選び方と相場
- 送る時期と注意点
読み仮名
香典返しとは
香典返しとは、 葬儀や法要で 香典(お悔やみとしていただく 金品)を受け取った 人に対して、 その感謝の気持ちを 込めて贈る 返礼品のことです。
いただいた善意に対し、 感謝と 故人の 供養の意味を 込めて「つまらないものですが…」という 日本らしい 謙譲文化から 生まれた 習慣です。
香典返しの目的とは
- 香典をいただいたことへの礼
- 故人の供養としての意味合い
- 社会的礼儀としての形式的な返礼
香典返しのタイミングとは
- ・即日返し(葬儀当日)
- 通夜や葬儀の 受付時に香典をいただいた その場でお返しを 渡す形式。 軽くて持ち 帰りやすいものが 選ばれやすい。
- ・後返し(忌明後)
- 四十九日や 一周忌などの 法要が 終わったあとに、 郵送などで 贈る方法。 より丁寧とされ、 関東では主流。
香典返しの相場とは
一般的には、 いただいた香典額の 半額(いわゆる「半返し」)が 目安です。 ただし、地域や 宗教、 家の考え方によっては、 3分の1に抑えることもあります。
香典返しの品物とは
- お茶(緑茶・紅茶)
- 和菓子・洋菓子の詰め合わせ
- タオルやハンカチのセット
- 洗剤・石鹸
- カタログギフト
「消えもの」が好まれるのは、 不幸を「後に 残さない」という 考えからです。
香典返しと粗供養の違いとは
香典返し:
香典をいただいたことへの
返礼
粗供養:
参列してくれたことへの
感謝の品
香典返しの地域差とは
- 関西:即日返しが主流
- 関東:後返しが多く、忌明後に郵送
宗派によっては 「香典返し」という 言い方を 避け、「返礼品」と 呼ぶこともあります。