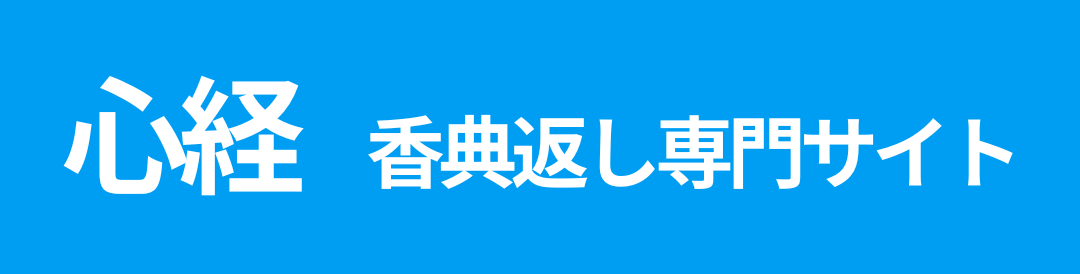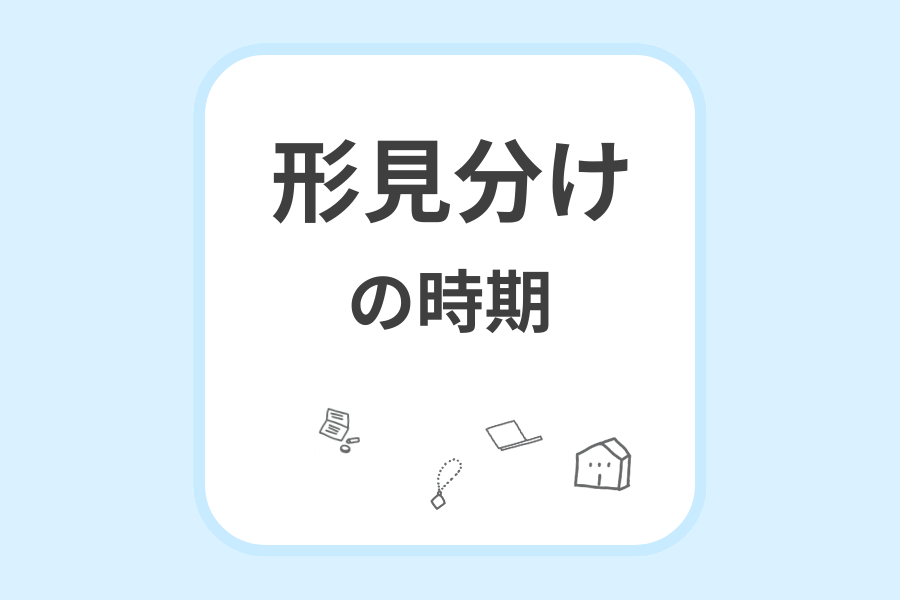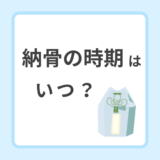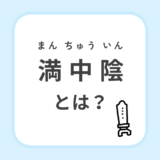目次 非表示
形見分けとは
形見分けとは、故人が生前に愛用していた品物を、遺族や親しい人に分け与えることを指します。
「故人を思い出し、身近に感じてもらうための行為」として、日本の葬送文化の中で大切にされてきました。
形見分けの時期とは
形見分けの時期には明確な決まりはありませんが、一般的な目安があります。
- 忌明け(四十九日法要の後)
多くの地域・宗派では、四十九日の忌明け後に行うのが一般的です。
これは、故人が成仏したとされる区切りの時期だからです。 - 百か日や一周忌の後
四十九日に間に合わない場合や準備が整わない場合は、百か日や一周忌のタイミングに行うこともあります。 - 葬儀直後は避ける
故人を失った悲しみが大きく、整理がつかないため、葬儀直後の形見分けは一般的には行いません。
形見分けの注意点とは
- 分ける相手:親族や特に親しかった友人などに限定することが多い
- 品物の選び方:故人の人柄を思い出させる日用品や愛用品が望ましい
- 配慮:高価なものや遺産とみなされるものは「遺産分割」の対象になるため注意が必要
- 包装:華美なものは避け、白い紙や半紙などで包むことが多い
地域差とは
- 関東では「忌明け(四十九日)」を待つことが多い
- 関西では「葬儀からしばらくして遺品整理の中で行う」ケースもあり、比較的柔軟
読み仮名
形見分けとは
形見分けとは、 故人が 生前に 愛用していた 品物を、 遺族や 親しい 人に 分け 与えることを 指します。 「故人を 思い 出し、 身近に 感じてもらうための 行為」として、 日本の 葬送文化の なかで 大切に されてきました。
形見分けの時期とは
形見分けの 時期には 明確な 決まりはありませんが、 一般的な 目安があります。
- 忌明け(四十九日)
多くの 地域・ 宗派では、 四十九日の 忌明けに 行うのが 一般的です。 - 百日や一周忌
準備が 整わない 場合は、 百日や 一周忌に 行うこともあります。 - 葬儀直後は避ける
悲みが 深く、 整理が 付かないため、 葬儀直後には 行わないのが 一般的です。
形見分けの注意点とは
- 分ける相手:親族や親しかった友人
- 品物の選び方:故人を思い出すものが望ましい
- 遺産とみなされる高価なものは注意
- 包装は白い紙や半紙を用いる
地域差とは
- 関東:忌明け(四十九日)を待つことが多い
- 関西:葬儀後の遺品整理のなかで行うこともあり、柔軟