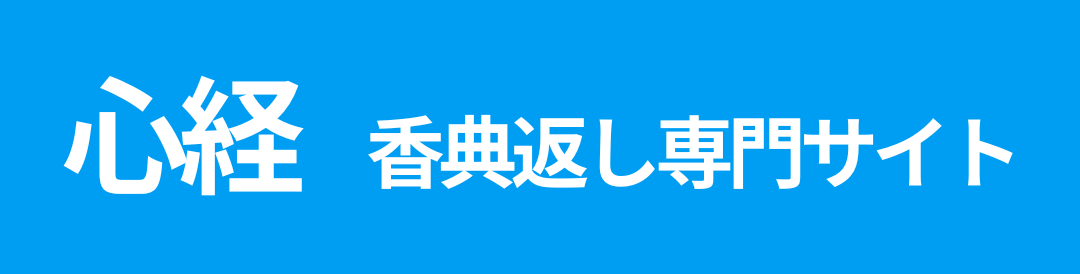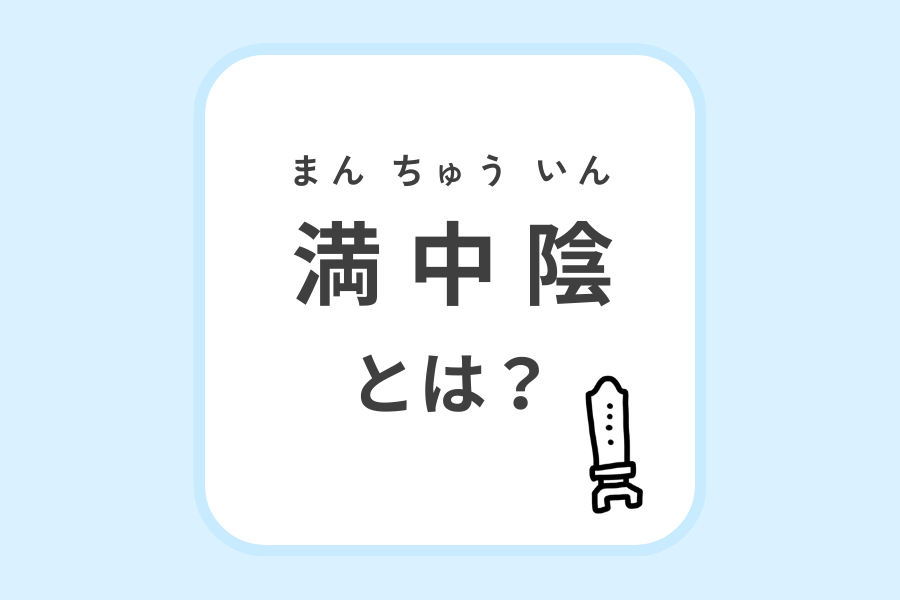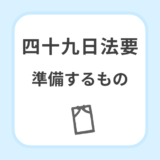満中陰とは
満中陰(まんちゅういん)とは、故人が亡くなってから四十九日目を迎えることを指す言葉です。
仏教において、人は亡くなった後、七日ごとに冥界で裁きを受けるとされ、その七回目、すなわち四十九日目で最終的な裁きが下り、成仏すると考えられています。
そのため、四十九日を「忌明け(きあけ)」と呼び、区切りとして特に重んじられます。
満中陰法要とは
満中陰には「満中陰法要(四十九日法要)」が営まれます。
・僧侶を招き読経をしていただく
・遺族・親族が参列し、焼香を行う
・法要の後に納骨を行う場合も多い
・参列者には「満中陰志」として返礼品を渡す
満中陰志とは
関西地方を中心に、満中陰法要に参列してくれた方へ渡す返礼品を「満中陰志(まんちゅういんし)」と呼びます。
関東では同じものを「志」や「忌明志」と呼ぶことが多いです。
満中陰の意味合いとは
- 故人が無事に成仏したことを祈る区切りの儀式
- 遺族にとって、喪に服す期間の一区切り
- 社会生活に戻る節目
地域差とは
・関西地方では「満中陰」という表現が一般的
・関東地方では「四十九日」や「忌明け」という言い方が多い
・返礼品の表書きも「満中陰志」(関西)と「志」「忌明志」(関東)で違いがある
読み仮名
満中陰とは
満中陰とは、 故人が 亡くなってから 四十九日を 迎えることを 指す 言葉です。 仏教では、 人は 亡くなった 後、 七日ごとに 冥界で 裁きを 受け、 その7回目、 すなわち 四十九日で 最終的な 裁きが 下され、 成仏すると 考えられています。
そのため、 四十九日は 「忌明け」と 呼ばれ、 区切りとして 特に 重んじられます。
満中陰法要とは
満中陰には 「満中陰法要」 (四十九日法要)が 営まれます。
- 僧侶を招き読経をしていただく
- 遺族・親族が参列し、焼香を行う
- 法要の後に納骨をすることもある
- 参列者には「満中陰志」として返礼品を渡す
満中陰志とは
関西地方を 中心に、 満中陰法要に 参列してくれた 方へ 渡す 返礼品を 「満中陰志」と 呼びます。 関東では 「志」や 「忌明志」と 呼ぶことが 多いです。
満中陰の意味合いとは
- 故人が成仏したことを祈る区切りの儀式
- 遺族にとっての喪に服す期間の一区切り
- 社会生活に戻る節目
地域差とは
- 関西では「満中陰」という表現が一般的
- 関東では「四十九日」「忌明け」という言い方が多い
- 返礼品の表書きも「満中陰志」(関西)と「志」「忌明志」(関東)で違いがある