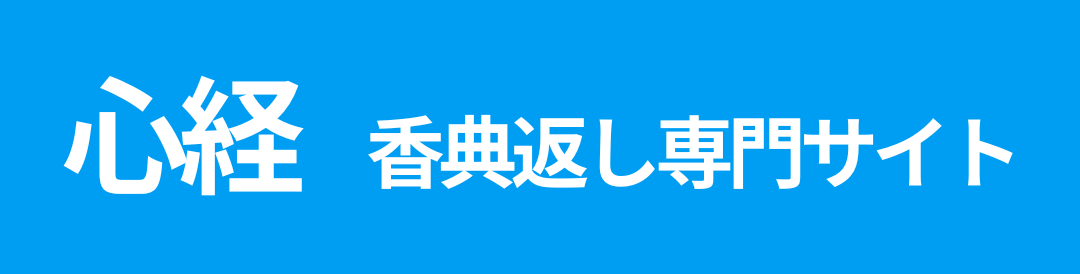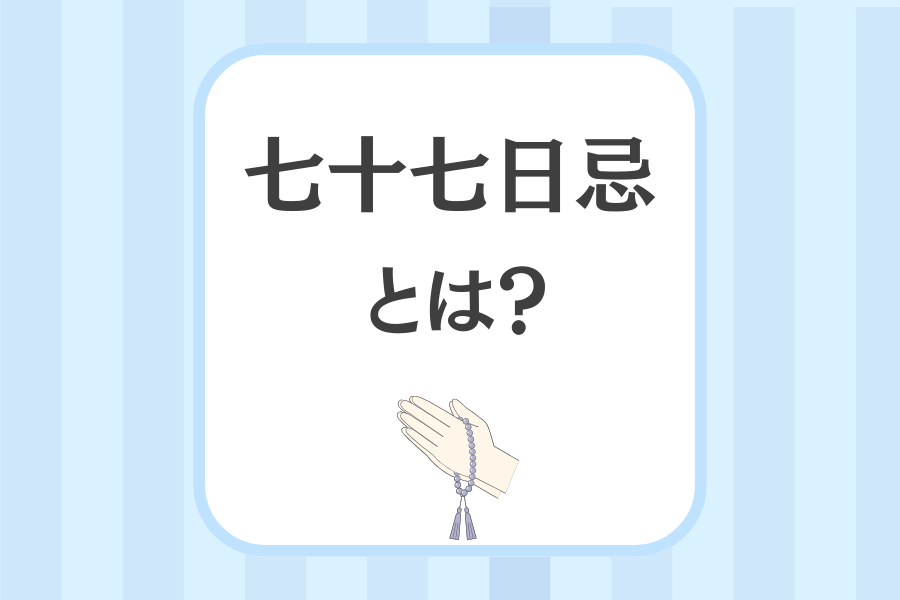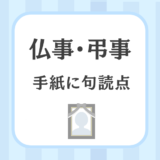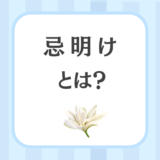「七十七日忌」は、故人が亡くなってから77日目(11週目)に営まれる仏教の忌日法要のひとつです。
「十七回忌(じゅうしちかいき)」とは別物であり、これは「中陰(ちゅういん)法要」の延長にあたります。
四十九日法要を過ぎると、法要は簡略化されていきますが、地域や宗派によっては「七十七日忌」を営む習慣が残っています。
意味と位置づけ
中陰の後の節目
- 四十九日までは7日ごとの法要(初七日〜七七日)が中心でした。
- 四十九日を「忌明け」として一区切りとしたあと、七十七日忌は補助的な法要です。
- 百箇日(ひゃっかにち)法要とともに、遺族が心の整理を深めていく過程とされます。
実施するかどうかは地域差・家族の意向
- 一般には行わない家庭も多く、省略されることもあります。
- 菩提寺や地域の慣習に従うのが一般的です。
いつ行うのか?
- 故人の命日を1日目として数え、77日目(11週目の忌日)に行います。
- 都合により、直近の土日などに繰り上げて行うこともあります。
どのように行う?
規模
- 一般には簡素に行われ、家族や親族など少人数で済ませる場合が多いです。
- 僧侶を招いて読経していただくこともあれば、家族だけで焼香と拝礼だけのケースもあります。
祭壇・供物など
- 四十九日と同様に、小さな祭壇を用意し、故人の遺影や位牌に供花・供物を捧げます。
- 仏具、線香、ローソクなど基本的な準備は必要です。
会食・返礼品
- 省略することが多いですが、行う場合は簡単な会食(精進料理)を用意します。
- 香典返しなどの返礼品は不要なことがほとんどです。
施主の心構え
- 四十九日後も故人を偲び、感謝を忘れないという気持ちを大切に。
- 宗教的な意味合いというよりは、「心の節目」「親族の再会の機会」としての意味合いが強まります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法要の名称 | 七十七日忌(しちじゅうしちにちき) |
| 行う日 | 命日を含めて77日目(11週目) |
| 意義 | 中陰後の補助的な法要、心の整理の節目として行う |
| 実施の有無 | 必須ではなく、地域や宗派、家族の意向により異なる |
| 規模・内容 | 簡素な読経や拝礼、必要に応じて祭壇・供物を用意 |
| 僧侶の招待 | 招くこともあるが、省略して家族だけで行うことも |
| 会食・返礼品 | 原則不要(希望すれば用意も可) |
読み仮名
七十七日忌とは
七十七日忌は、 故人が亡くなってから 七十七日目に営まれる、 仏教の忌日法要のひとつです。
意義と位置付け
四十九日の忌明けのあとに行われる、 補助的な法要です。 遺族の心の整理や 故人を偲ぶ機会としての意味があります。
日程
命日を1日目として数え、 七十七日目に行います。 都合により前倒しすることもあります。
法要内容
- 規模:家族や親族のみで簡素に営むことが一般的です。
- 読経:僧侶を招いて読経を依頼するか、家族だけで焼香・拝礼を行う。
- 祭壇・供物:遺影や位牌を飾り、供花・果物・お菓子などを供える。
会食・返礼品
省略されることが多いですが、希望すれば 簡単な精進料理を用意します。 返礼品は不要なことが一般的です。
施主の心構え
故人への感謝と、日常生活への 心の切替の節目として捉えます。 宗教的というよりも、精神的な整理の機会としての意味合いが強いです。